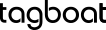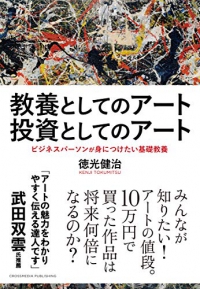アートの情報は「ケチる」べきではない
アートの展示作品は基本的に「売ること」が目的である。
これは言うまでもないことであり、ギャラリーにとっても、作品を購入してもらうことが次の展示へとつながる重要な要素である。
しかし、ギャラリーのウェブサイトやSNSを見ると、展示作品の一部しか掲載されていないことが多い。
「なぜ全部見せないのか?」
この疑問は、多くのアートファンや潜在的な購入者が抱えていることだろう。
作品を買うかどうかを決める前に、もっと情報がほしいと思うのは当然のことだ。
しかし、ギャラリーはなぜかすべての作品を公開せず、一部の画像だけを載せることが多い。
かつて、ギャラリーは「予告編」のように一部の作品だけを見せ、残りは「ギャラリーに来てのお楽しみ」という戦略をとっていた。
映画の予告編が本編の一部だけを見せて観客の興味を引くように、展示の全貌を明かさないことで「実際に来て確かめてほしい」という思いがあったのだ。
しかし、この考え方は、インターネットが発達した今の社会では、もはや時代遅れと言わざるを得ない。
「余計なものを見せない」は正しいのか?
ギャラリーが展示作品をウェブに公開しない理由のひとつとして、「展示空間の美しさ」を守るためという考え方がある。
作品が並ぶギャラリーでは、空間全体のバランスを考え、余計な要素を極力排除する。キャプションや説明文を最小限にとどめ、純粋に作品だけを楽しんでもらいたいという意図があるのだ。
これ自体は理解できる。実際、展示会場では作品以外の情報が目に入らないことで、鑑賞者はより集中して作品と向き合うことができる。
しかし、これは「展示空間での話」であり、ウェブ上の情報とは切り離して考えるべきだ。
展示では余計なものを排除することが大切だが、それと同じように、ウェブやSNSでは「必要な情報を伝えること」が大切なのである。
ギャラリーの目的は作品を売ることなのだから、ウェブ上では情報を削るのではなく、むしろ積極的に提供すべきである。
価格を隠すことの不信感
もうひとつ、アートギャラリーがよくやることとして「価格を隠す」という問題がある。
価格表が公開されていないため、購入希望者はスタッフに声をかけなければならない。しかし、これは日本人にとって非常にハードルが高い。
「すみません、この作品はいくらですか?」と尋ねるのは、知らない人と話すのが苦手な日本人にとってはかなり勇気がいる行為である。
しかも、価格を聞いた途端に「高いですね」と思っても、後に引けなくなることがある。
こうした心理的な壁があるため、アートに興味があっても購入に至らない人が多いのだ。
さらに、価格が公開されていないことで、二重価格の疑念を抱かれることもある。
つまり、常連には安く売り、初めての客には高く売るだけでなく、国内と海外でも価格差があるのではないか という不信感である。
実際に、日本国内では比較的安く販売されている作品が、海外では倍以上の価格で取引されている例も少なくない。
海外のマーケットのほうがアートに対する評価が高く、価格も上げやすいため、ギャラリーは国内では価格を抑え、海外ではプレミア価格で販売することがある。
しかし、こうした価格の不透明性が、国内のアートファンやコレクターの不信感を生む原因にもなっている。
展示空間を守りつつ、価格情報は公開するべき
価格の情報を見せたくないというギャラリー側の意図も理解できる。
展示空間では、価格情報が視界に入ると、作品そのものを楽しむ妨げになることもある。作品の価値が金額だけで判断されることを避けたいという気持ちもあるだろう。
しかし、それならば、「価格は見せない」のではなく、「価格を見やすくする」工夫をすべきである。
たとえば、
展示空間には価格情報を載せず、ギャラリーの入り口や受付近くに一覧表を掲示する
ウェブサイトに全作品の価格を掲載し、事前に確認できるようにするデジタル端末で価格一覧を自由に閲覧できるようにする
重要なのは、価格表が「誰でも見られるもの」であること である。
ギャラリーのスタッフに頼まなければ価格がわからないという仕組みは、購入のハードルを上げるだけでなく、「価格は特別な情報なのではないか?」という不信感を生む原因になる。
特に、日本の文化では、知らない人に声をかけることに抵抗がある人も多い。価格情報を自由に見られるようにすることで、顧客と作品の距離を縮めることができるのだ。
アートの情報は「ケチる」べきではない
ギャラリーは、展示空間では作品だけに集中できる環境を整え、余計なものを排除することが重要である。
しかし、それと同時に、価格情報や作品の詳細情報は「必要なもの」として、誰もがアクセスしやすい形で提供すべきである。
「展示は作品だけを見せる場であり、余計な情報は載せたくない」という考え方は理解できるが、それを理由に価格情報を隠してしまうのは、顧客にとって不親切であり、業界全体の信頼を損なうことにもつながる。
情報を開示することで、顧客がより安心してアートに触れることができる。そして、それがギャラリーやアート市場の成長にもつながるのだ。
ギャラリーが「来てのお楽しみ」と言う時代は終わった。
今の時代は、「情報を見たからこそ、行ってみたい」と思わせることが求められている。
アートは、ただ作られたから売れるのではなく、「見せる努力」をすることで価値が生まれるのだ。
情報を出し惜しみしている場合ではない。
今の日本のアート市場を成長させるために、まずは「見せること」から始めるべきなのではないか。
コラム著者のX(Twitter)はこちら
https://newspicks.com/topics/contemporary-art/
2025年2月21日(金) ~ 3月11日(火)
営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝
※初日2月21日(金)は17:00オープンとなります。
※オープニングレセプション:2月21日(金)18:00-20:00
入場無料・予約不要
会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F
tagboatのギャラリーにて、現代アーティスト手島領、南村杞憂、フルフォード素馨による3人展「Plastics」を開催いたします。「Plastics」では、表面的な印象や偽りの中に潜む本質を提示した3名のアーティストによる作品を展示いたします。